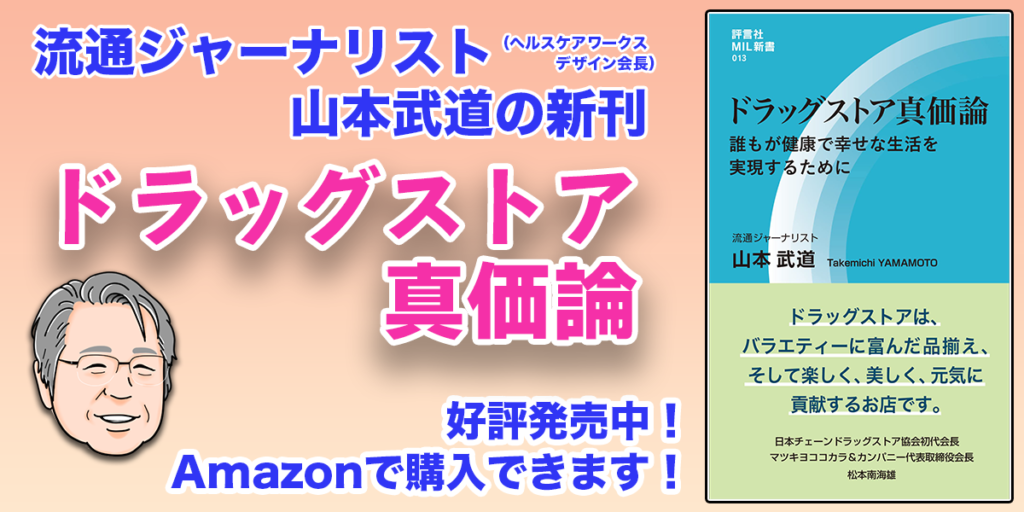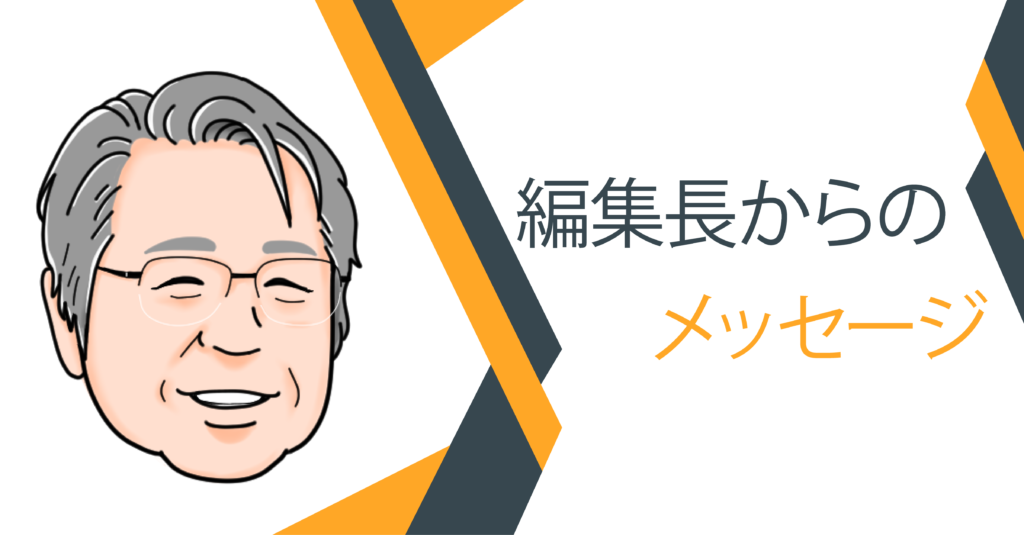日本対がん協会が6月1日、『がんとともに生きる‐転移・再発した私の「わたしらしく」を考える』テーマに『JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025』
日本対がん協会は6月1日に、がん患者さんと家族が必要な支援に辿り着くための情報を提供するイベント『JAPAN CANCER SURVIVORS DAY 2025(ジャパンキャンサーサバイバーズデイ)』を開催します。8回目となる今年のテーマは、『がんとともに生きる ‐転移・再発した私の「わたしらしく」を考える』。


「がんという病気により、こころや身体にさまざまな変化がおこりうる中にも「わたしらしく生きる」ためのヒントにたどり着けるように、専門家による講演やブース展示などを通して情報をお届けします。あなたにとっての「わたしらしく」を、一緒に考えていきましょう」(日本対がん協会)
詳細は以下の通り。
◾︎日時:2025年6月1日(日)10:30~15:30(開場10:00/閉場16:00)
◾︎場所:国立がん研究センター 築地キャンパス 研究棟
◾︎参加費:無料
◾︎ライブ配信無し/後日YouTubeにてアーカイブ配信予定
▼詳細・申し込み:https://www.gsclub.jp/jcsd2025
がんサバイバー・クラブの問い合わせメールアドレス変更のお知らせ
がんサバイバー・クラブの問い合わせメールアドレスが、4月1日から以下の通り変更になりました。
◾︎新しいメールアドレス:gsc@jcancer.jp
女性医療ネットワーク マンマチアー委員会第172回が4月30日、
『多様化する乳房再建とその後のケア〜喪失、変形した乳房、
乳頭乳輪の再建法と術後ケア』テーマにオンライン開催
◾︎開催日時:2025年4月30日(水)18時半〜20時
◾︎開催方法:ZOOMによるオンライン
◾︎参加費:無料(申込み先着120名)
◾︎テーマ:『多様化する乳房再建とその後のケア〜喪失、変形した乳房、乳頭乳輪の再建法と術後ケア』
◾︎スピーカー:小宮貴子さん(東京医科大学形成外科学講座 准教授 同大学病院 形成外科)
◾︎内容:乳がんは病の怖さに加え、女性の特徴といえる乳房の喪失や変形がついて回ります。「乳房再建」は、失った乳房や乳頭乳輪を作りなおし、喪失感を補い、その後の長い人生に寄り添うための医療です。乳房再建には自家組織再建、インプラント再建のほか、脂肪注入(自由診療)や乳頭乳輪の再建にも様々な方法がありますが、最近は自家組織再建×インプラント、部分切除の方の再建など、その方の状況によってカスタマイズもはじまるなど再建法も多岐にわたります。
前回大好評だった再建後の乳房のケアや下着のことなど、女性医師ならではの視点でお話いただきます。「教科書的な説明ではなく、生活にフィットさせた生きた情報をお伝えします」(小宮先生)
大前提として乳房再建は、してもしなくてもいいもので、ご自身の価値観を最優先に選択するものです。再建を望む方はもちろん、迷っている方、いつかは再建をしたい方。再建する気はないけど知りたい方、それぞれの立場で考える時間になればいいと思います。前質問にもお答えいただきます。ぜひご参加ください。
【小宮子先生略歴】
2002年:東京医科大学医学部医学科卒、2008年:東京医科大学形成外科学講座助教授、2011年:医療法人社団ブレストサージャリークリニック勤務。2015年、医学博士取得、東京医科大学形成外科学講座講師。2022年、同准教授。現在、東京医科大学病院、同大学茨城医療センター、同大学八王子医療センターにて乳房再建に従事。
2年前より厚生中央病院にて乳頭乳輪再建をメインに取り組むなど、乳房のふくらみだけでなく、乳頭・乳輪の再建にも力を入れている。「患者さんが安心して乳がん治療に引き続き再建できること」を理念に掲げる。
2024年、日本形成外科学会編「患者さんと家族のための乳房再建ガイドブック」作成委員の班長を務める。日本形成外科学会専門医・指導医、再建・マイクロサージャリー分野指導医、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会評議員、創傷外科学会専門医、乳房再建用エキスパンダー/インプラント責任医師。
◾︎参加費:無料(先着120名)
◾︎ZOOM参加申込み方法: https://mammacheer172.peatix.com/
申し込み開始しております。開催前日までにZOOMのURLをお送りいたします。
<申込み締め切り>2025年4月29日(火)18時まで
★このメールへの返信では申し込みできませんのでご注意ください。
●申込み時には姓名(ニックネームではなくフルネーム)での参加登録をお願いします。
●後日の録画配信はありませんので、予めご承知おきください。
●申し込み後、参加できなくなった方は、キャンセルをしていただけますと、ほかの方が参加できます。
●当日のZoom URLなど詳細は、前日より申込みいただきましたPeatixページの「イベント視聴ページ」で確認できます。当日までの各種ご案内はPeatixメール(@peatix.com)より配信されます。
*今後の予定や開催方法はその都度、登録されている方はメールと、マンマチアーのFacebookなどで案内させていただきます。
●諸事情により、急遽変更があった場合、申し込み者の方にメールおよびFacebookにてご連絡させていただきます。
*チアー活動”は乳がんを体験した、していないにかかわらず、どなたでも参加できます。男性や学生さんの参加、応援も大歓迎。
*マンマチアー(Mamma Cheer)委員会:NPO法人女性医療ネットワーク「マンマチアー(Mamma Cheer)委員会」は、乳がんを体験し、NPO法人CNJ認定乳がん体験者コーディネーターの美容ジャーナリスト・山崎多賀子さん、女性医療ジャーナリスト・増田美加さんが主宰・企画し様々な活動を行っています。アドバイザーとして対馬ルリ子さん(対馬ルリ子女性ライフクリニック院長)、片岡明美さん(乳腺外科医)の2人の医師も加わっています。
*マンマチアーは、無料開催にあたり、ボランティアで行っております。
●NPO法人女性医療ネットワーク事務局:https://cnet.gr.jp/
「8割以上の患者さんが根治的化学放射線療法の直後であっても再発に対する不安を感じていた」 アストラゼネカが切除不能局所進行非小細胞肺がん患者調査
62名のうち8割以上の患者さんが、根治的化学放射線療法の直後であっても再発に対する不安を感じ、再発に不安を感じていた人のうち4人に1人は時間が経過しても再発に対する不安が和らぐことはなかったーアストラゼネカ株式会社が実施した調査で明らかになりました。
この調査は、診断から5年未満かつ手術を受けていないステージ IIIの肺がん患者さんのうち、初回治療で化学放射線療法を受けた、あるいは受けていないが検討したことがある62名を対象に、治療前後に抱く不安や心情について調べるインターネットで調査したもの。
同調査から、化学放射線療法を受けた後でも、再発に対する不安を感じる患者さんが 8 割を超え、このうち4人に1人が時間が経過しても再発に対する不安が残り続けることが示されました。
「肺がんは日本人の部位別のがん死亡数がもっとも多いがんであり、ステージIIIの5年生存率は28.6%(国立がん研究センターがん情報サービスがん種別統計情報「肺」及び国立がん研究センターがん情報サービス院内がん登録生存率集計結果閲覧システム肺がん2014-2015年5年生存率より)です。
ステージIIIの肺がんは根治を目指した治療となり、一部(ステージIIIA)は切除手術が行われますが、切除手術ができない場合は化学放射線療法が標準治療となります(国立がん研究センターがん情報サービス「肺がん 非小細胞肺がん治療」より)」(アストラゼネカ)
調査結果のサマリーは次の通りです。
(1)化学放射線療法を受けるかどうかを決める際に参考とした情報源には、「医師からの説明」が 96.8%と大半を占めた。
(2)化学放射線療法を受けると決めた理由は多岐にわたり、「医師の勧め」のほか、「治療効果への期待」「手術の難しさ」「選択肢の制約」などの理由が挙げられた。
(3)化学放射線療法を受けた患者さんの 41%はつらい治療であると感じた一方で、治療選択したことを後悔していないと回答した患者さんは 94.8%に上った。
(4)根治目的の化学放射線療法後、再発に対して不安を感じている患者さんは 84.6%であり、治療直後に不安を感じていた患者さんの 24.2%が、再発に対する不安を変わらずに持ち続けていた。
ちなみに同調査の趣旨は、初回治療として化学放射線療法を受けた、あるいは受けていないが検討したことがある肺がん患者さんの治療前後に抱く不安や心情を把握するためにインターネット調査委託先:株式会社メディリード)で行われた(期間:2024年12月11日~2024年12月31日)。
調査対象は、診断から5年未満かつ手術を受けていないステージIIIの肺がん患者さん 62名、初回治療で化学放射線療法を受けた方39名、受けていないが検討したことがある肺がん患者さん23名。
調査監修は、加藤晃史医師(神奈川県立がんセンター呼吸器内科)原田英幸医師(静岡県立静岡がんセンター放射線治療科部長)長谷川一男理事長(NPO 法人肺がん患者の会ワンステップ)
調査結果の詳細は、https://www.astrazeneca.co.jp/content/dam/az-jp/press-releases/pdf/202503_nsclc.pdf
子供たちの健康リテラシーを目指し活動35年
OTSUKA まんがヘルシー文庫『くすりのおはなしの巻』発刊
OTSUKAまんがヘルシー文庫『元気のお手伝い!くすりのおはなしの巻』を発刊し全国の小学校に寄贈する大塚ホールディングスの活動は子どもたちの健康への寄与を目指して毎年行っているもので、1989年(平成元年)の創刊から35年を迎える今回は、『元気のお手伝い!くすりのおはなしの巻』を発行されました。

OTSUKAまんがヘルシー文庫は、日本医師会、日本学校保健会の監修のもと、日本小児科医会の推薦を受け毎年新刊を発行し、全国の公・私立の小学校や特別支援学校、海外日本人学校、国公立図書館などに寄贈している大塚グループの社会貢献活動。毎年、体のつくりや健康・栄養に関するテーマを決め、医師や教諭などの専門家が構成を担当し著名な漫画家が楽しい漫画に描きおろしています。創刊から35年間に196人の専門家と、37人もの漫画家が制作に携わり、寄贈した文庫はおよそ130万冊となったそうです。
最新刊の『元気のお手伝い!くすりのおはなしの巻』は、薬の役割や体内での働き、正しい使い方など子供たちに伝えたい内容を、6人の漫画家がオリジナルのストーリーで楽しくわかりやすく漫画にしています。章のまとめとして、理解を深めるためのクイズやすごろくのページを配し、子どもたちが得られた知識を自分の日常につなげる工夫を施しました。テーマに合わせ毎年募集している児童作品も、各章の大切な要素として掲載されページを盛り上げています。
「同文庫のWebサイトには、これまで発刊した35冊の漫画から約120編を電子化し掲載されています。子供たちの興味に合わせて読みたい漫画を検索しやすくするとともに、季節や健康状況をふまえたお勧め漫画を提案し、子供たちの健康への関心と知識を深めています。
学校関係者対象のページでは、当文庫を健康教育や教科学習に役立てていただくため小学校学習指導要領との対照表を作成し掲載しているほか、子どもたちが作品掲載を通じてヘルシー文庫づくりに参加できる児童作品募集の情報提供、学校現場との情報交換を目的とした健康学習活用研修会レポートも紹介をしています。
活動35年の節目を迎え、今後も、文庫とWebサイトの充実をはかり、子どもたちの健康に役立つ活動を継続してまいります」(同社)』
◾︎これまでに参加した漫画家
赤塚不二夫、秋竜山、あべさより、石ノ森章太郎、一本木蛮、いわみせいじ、岡部冬彦、おぎのじゅんこ、おのえりこ、かなき詩織、幸月さちこ、小山賢太郎、里中満智子、鈴木太郎、鈴木義司、竹宮惠子、種村国夫、ちばてつや、所ゆきよし、永野のりこ、二階堂正宏、馬場のぼる、浜田貫太郎、林家木久扇、原子力、ヒサクニヒコ、前川かずお、前川しんすけ、まちやまみつひろ、松本零士、間部正志、百田まどか、やなせたかし、山口太一、柚月ナナ、横山ふさ子、横山隆一 (敬称略・50音順)
◾︎取り扱ったテーマ例:食と栄養、体のつくり(臓器)、体の不思議(仕組み)、病気、運動・スポーツと健康、けがと応急法、 感染症、健康と心、細菌・ウイルス、水と健康、地球環境と健康、生活習慣と体のリズム、健康診断、学校安全・交通安全・災害安全、100歳まで元気に、皮ふの健康など
OTSUKAまんがヘルシー文庫Webサイト:https://www.otsuka.com/jp/comiclibrary/